2021/05/01
萩尾望都先生の冷凍された荒ぶる神
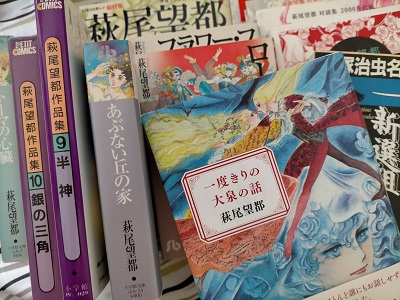
前回にわかに萩尾望都先生の世界を再発見して、色々と借りたり買ったりして読んでいます。
新しく読んだもの
『恋するあなた*恋するわたし」対談集2000年代編
『マンガのあなた*SFのわたし』対談集1970年代編
『萩尾望都 紡ぎつづけるマンガの世界』
『手塚治虫文化賞作家が選ぶBestof手塚's work』
『文藝別冊 総特集 萩尾望都』
『新選組』手塚治虫
『フラワー・フェスティバル』
『海のアリア』
『バルバラ異界』
持ってた
『半身』『トーマの心臓』『ローマへの道』『銀の三角』『残酷な神が支配する『感謝知らずの男』
友人が貸してくれた
『危ない丘の家』
『11人いる!』
『一度きりの大泉の話』
なぜ読みたい知りたいと思ったか。
それは、なぜ自分が今まで「萩尾望都にぴんとこなかった」のか知りたかったからです。
物事は、比較対象によってよく見えるもの。
『花咲く乙女たちのキンピラゴボウ』の、萩尾望都、山岸凉子、大島弓子論を再読して、もしかしてこうなのかなと感じました。
大変失礼な言い方になりますが、つまり、つまり自分にとって、萩尾望都先生は
『カマトトぶっている』
と映ったのではないかと。
カマトトぶるとは知っているのに知らないふりをする、無垢を装う事をさします。
つってもピンと来ないですか。
私も来ない(笑)何といったらいいのかつまり
少年の未分化の性における愛、世界から隔てられた永遠の喪失、母親を憎んでも直接憎しみをぶつけず自ら手を下さず殺す事、少女たちの無自覚な鈍感さ、己の体の内にある醜悪さへの嫌悪ではなく、醜悪は他者から与えられるものであること
そういったものが、子どもの私には何かから目を背けていると映ったのです。
山岸凉子先生の、アラベスク二部の、少女の人間としての自立と孤独と愛と性の相克、大島弓子先生の、どうして自分は女なんだろうどうして世界はこうなんだろうという己の内実を突き刺すようにして描き出す作品は、よろめきながら人間として立ち世界と戦い生きるすべをみいだしたかった子どもの女の自分にとっていっさいのごまかしがなく目を開かせてくれるものでした。
萩尾先生の作品は、美しい子どもの世界で、それが失われていく情感が幾ら美しくても、毒のなさと覆い隠すなにものかとみえ、距離があったのです。
女性に対する制約が大きく男の子にしたら自由で描きたいものが描きやすかった。と仰っていましたが、女性に対する制約を山岸・大島先生が分解しよう、人目にさらそう、そこからどう生きるか考えよう、として描いていたのに対し、そのままでいい、と冷凍して、自分だけ自由の中にいるように感じたのかもしれません。
大泉の話を読んで、萩尾先生は怖い人だと思いました。
初めて読んでみた作品群からも、何か深い、人にわかる形で出す事すらできない濃くて重い、どす黒いと言っていいものがあるように感じました。
先生自身も、日本を舞台にすると家の事を思い出してしまう、とおっしゃっていましたが、『フラワー・フェスティバル』『バルバラ異界』に登場する母親の自己中心的なヒステリックさはほとんど病気の域。
あと、全般的に女性が好きではないのかな、とか。
男同士の恋愛に近い繊細な感情の交流はあるのに、女同士のそれはない。
男性に自己投影し、女性を敵役か都合のいいマスコット的な存在にし、自分はそういう女性たちとは違うといわんばかりに描くというのはよくありますが、それに近い部分もあるような気がしました。
前回、萩尾先生は、両親という他者の理不尽に対して怒りではなく痛みとなぜ?を持ち続けているのではないかと書きました。
でもそうではないかもしれないな?と思った。
萩尾先生自身が、激しい怒りを感じてしまうのでそれを心の底に押し込めてしまう、怒りに支配されないように、と大泉の話で書かれていたからです。
そして、色々なことを決して許していないのだな、赦さず忘れずにいるのだなと。
当時の事は冷凍している、と書かれていたのが印象的です。
DVや虐待を受けた人は、その痛みから逃れるために心の中で凍らせるのだと精神科医が言っているのを聞いたことがあります。とても向き合えないので冷凍してなかったことにしてしまう。
冷凍された痛みは、何かの拍子で解凍して当時のままの痛みを与えてくる。
だから決して癒えることがない。
子どもだった私は人間として正しい成長や痛みと向き合い乗り越えることを欲していた。求めていた。それが正義だと思っていた。
でも大人になって、そうではないものがあることを知りその正しさも受け入れられるようになった。
今、萩尾望都先生を知りたいと思うのはそういう事なのかなと思います。
あと、萩尾先生が無垢で残酷な天才であり、おだやかで完璧な神ではなく、心の底に荒ぶる、人を許さず痛みを冷凍しておく頑なさがあることも、僭越ですが創作者として魅力的だと感じました。
大泉の話は、好きなものが同じ人同士で語るのは楽しいけれど、そこに村社会や狭い人間関係で力関係ができてくるとしんどいなという実感です。
もう絶対関わりたくないよね。オタク同士の話とか、気の合う二人か三人くらいでするもんだよ。
同担拒否や地雷や腐女子的ルール、大切にしているジャンルに無造作に踏み込まれる怒りと誰のものでもないのになぜという感覚はわりとどちらも想像ができる気がしました。嫉妬というより、わからないのに入ってこないで(しかも世間でより優れたと言われるような「人間愛」的解釈にしてしまわないで)という気がするなあ…
萩尾先生は何度も、少年愛に興味はない、理解できないし好んではいないと仰っていましたが、漫画家を志されたきっかけという手塚治虫の新選組の深草丘十郎と鎌切大作の関係性はBL的な側面があって、竹宮先生とは解釈や好みが違うだけなのではと感じます。
私は男同士が好きなの、とカラっという山岸先生の方が、BLという枠ではなく女を人間を俯瞰して描かれている気がします。
竹宮先生が普通の(腐)女子であるのに対し、萩尾先生はもっと得体の知れない怖い神。傷つきやすい神。とても傷つかれたのだろうし理不尽に怒りや悲しみを覚えたのだと思う。でも人は理不尽なものです。親も理不尽です。そして、それへのアプローチをどうしようもできずに心に抱えたまま距離を取り冷凍するしかない萩尾先生の天才は、読者にとっては賜物なのだと思います。
あと、山岸先生はすごいよね…神目線でフェア
山岸先生について考えられないのは信者だからかなあ…
萩尾先生を心の中で本当に大切にされているには大変申し訳ありませんでした。
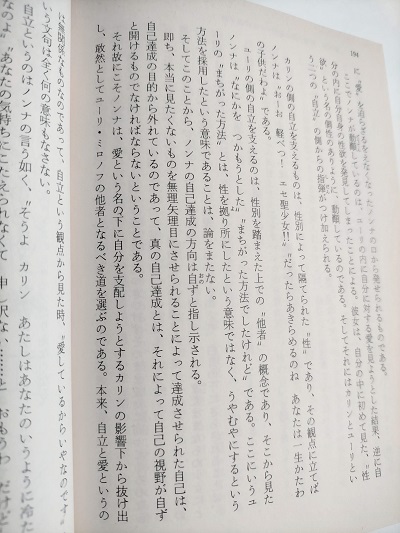
『花咲く乙女たちのキンピラゴボウ(上)』より
少女であるノンナが、人間として性と自立に直面し、愛の名を冠した支配から抜け出て、敢然と恋する相手の他者である道を選ぶ、というアラベスク二部評
とても好き。恋愛とは、同性でも異性でも人間として自立した者同士の間にあるのだという山岸先生の想いとそこに至るノンナの道は少女漫画のビルディングストーリーで最上のものであると思います。