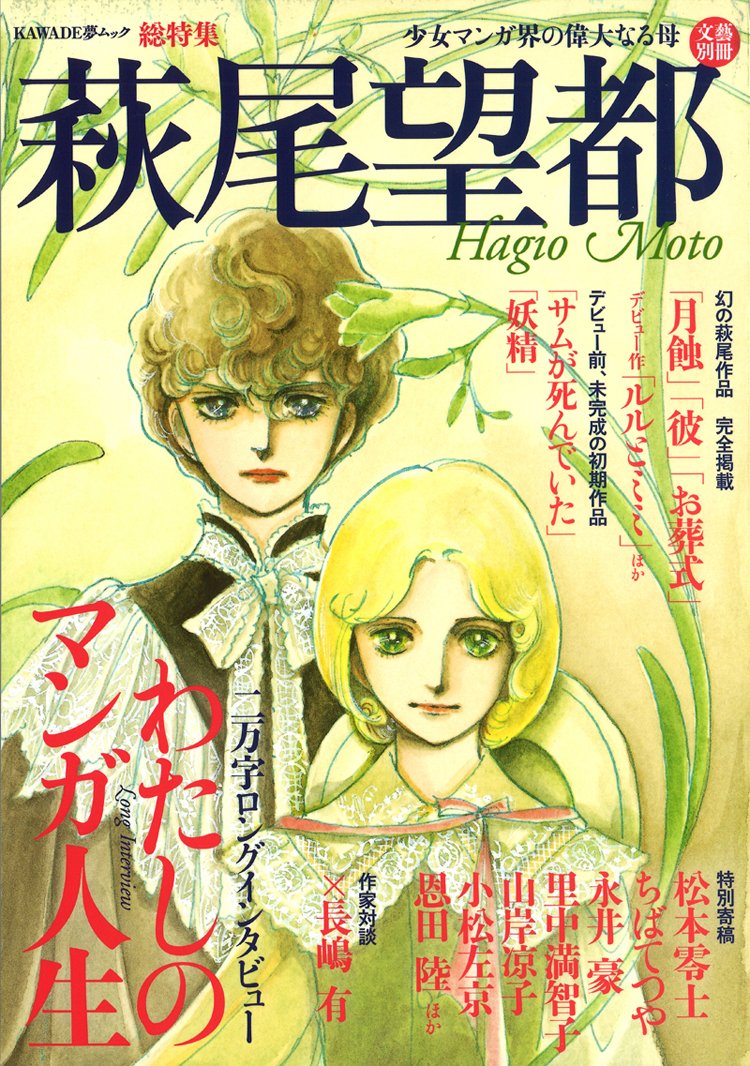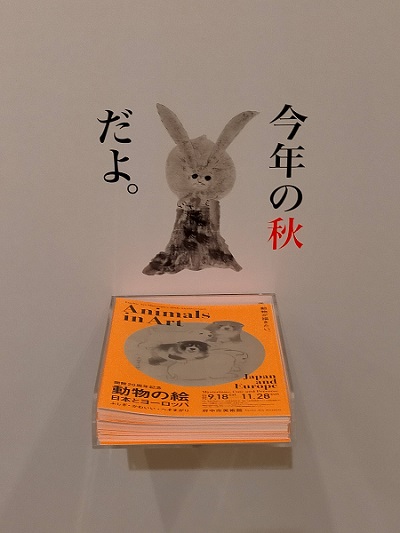2021/04/15
NOMADLAND
2021 アメリカ
監督: クロエ・ジャオ
原作者: ジェシカ・ブルーダー
音楽: ルドヴィコ・エイナウディ
映画館を出て友人と最初に交わした言葉
「運転免許取らなきゃ」
「そうだね、免許必要だね」
自分の能力を信用していないので、人を巻き込んで事故を起こしたらと思っていましたが、大自然で人けがないとこなら大丈夫、自由のために免許が必要な場合もあるな、と。
見る人によって受け取るものが違ってくる映画です。
おそらくどの表現作品もそうだろうと思いますが、この映画は見る側が何を自分の中に持っているかで受け取るものがかなり違ってくると思う。語られることより語られない事の方が重要で、人生や社会が複雑に絡み合っているので、経験や価値観によって視点の置き場が変わってくる。
個人的な所感
・主人公ファーンのキャンピングカーで季節労働をしながらの放浪生活は、喪失をきっかけとしているけれど、もともとそういう方向性の人間だったのであり、ノマド仲間も、社会からこぼれ落ち余儀なくされたのではなく、そういう人生を選ぶ人たちなのだと思う。最底辺でも悲惨でも落伍者でもなく、彼らにとってはデメリットもあるが、選びたい生活。
西行法師の「願わくば花の下にて春死なん」です。
少なくともファーンが関わる人々はそのように描かれています。
彼らは放浪生活のスキルを共有し、相互扶助しつつ、「訪問お断り」「寄ってかない?」「散歩してるからいい」と個の領域を優先する。
排他的な連帯や絆をもたない。人ではなく犬と旅する。
デイブは違います。
彼はファッションノマドです。だから息子夫婦の家に帰り裕福な屋根の下でまた定住を始め、車のタイヤがパンクしているとファーンに言われても「ああそう、もうどうでもいい」と流すことができる。
故障した車を手放して新しいのを買った方がいいと言われたファーンが「それはできない。手をかけてつくりかえてきたの。私の家なの」と断るシーンとは対照的です。
※ファーンとデイブ以外の出演者は、役者ではなく本物のノマドの人たちなのだそうです。
・人生はある地点まで、人間関係や地位やお金や不動産やキャリアなどさまざまなものを積み重ねていくものだけれど、どこかでそれを一つずつ手放して、失っていくものだと思う。そしてそれは寂しいことではなく、当然の、自然で、そう思って受け入れていけるかどうかが生き方を大きく左右するものだと思う。
残るのは、思い出だけ。
だから、スワンキーが、病気でもうすぐ死ぬのだといいながら、今までの人生で見た美しいものをいくつも言葉にしたとき、ああ、人生で真に必要なのはそれ以外にある? と思い、命の終わりが近づいたとき、どれだけ美しいものを見てきたかを思い出せる人生を送りたいと思いました。
・原作はノンフィクションで、高齢ワーカーがどのように巨大企業に搾取されているかを取材しているのかもしれない(読んでない)。おそらく語り方は映画と違うのでしょう。
映画ではアマゾンの工場は非人間的な現場と絵面では感じるが、働くノマドたちにとっては「稼げる悪くない場所」です。
ビーツの収穫でも巨大な非人間性システムを垣間見ることができる。
だが、人間はもはや自給自足で生きていく事はできない。
少なくとも文明社会の恩恵を受けている以上、ノマドたちも同じ。綿を育て服を自分でつくり、小麦を栽培してパンをつくり、車をつくり石油を採掘することは一人ではできない。排泄物を処理することもできない。
それらは分業で、巨大なシステムに依存することで相互補助の社会をつくりあげている。そのシステムが人を搾取しないように努力しなければならないけれど、個人の手が届かない怪物でもある。私たちは怪物に寄生して生きている。
一人で放浪するデメリットを知っているノマドたちはだからシステムの一部に依存し、責めることはない。
だが、それと、強欲を抑制せず意識的に人を踏みつける個人は違う。だからはっきり意見する。
ファーンが、姉夫婦の同僚の不動産関係者の「土地は儲かる。サブプライムローンの時もっと儲ければよかった」に対して「それは違う。返済能力のない人に借金をさせるのは、おかしいでしょう」と言うのは、そういうことである。
普通の、富裕な生活をしている姉夫婦にとっては厄介な義妹、だけれども、お姉さんがまともないいお姉さんでほっとしました。
・人を疑っているので、カリスマノマド氏がいつカルトのボスみたいになるのかとはらはらした。
人が誰かを見下したり利用したり故意に傷つけたりしない、やさしい話でした。
風景が美しい。人間がいない世界はほんとうに美しいね(滅びの呪文)
音楽がとても良かったです。ピアノ。
音楽担当のルドヴィコ・エイナウディはイタリア政府音楽大使で、祖父ルイージ・エイナウディはイタリア共和国第2代大統領を務めた経済学者だそうです。
教養と教育の正しい形…
クロエ・ジャオ監督も非常に教養の深い、どんな人へも敬意のある、知識ではなく知性を持つ方なのだろうと感じました。30代でこの映画を撮れる成熟度がすごい。
スワンキーのインタビュー
「この映画に出演するために、実生活の状況を少しの間、忘れることにしました。出演してよかったです。ジャオは、なんと、わたしの腕のギプスのことも映画の筋に入れてくれました。素晴らしい人でした」
フランシス・マクドーマンドは「まるでわたしが有名な映画スターで、彼女がわたしの熱烈なファンであるかのようにふるまってくれました。“一緒に映画に出られてとても嬉しい”と言ってくれました。なんだか、長い間離ればなれになっていた旧友に再会したような気持ちになりました。撮影中は今までに感じたことのなかったような愛、存在意義、感謝を感じました」
引用元 シネマカフェ 記事
わかりやすい、言葉にしやすい、多くの共感を得る作品は、受け手のポテンシャルに任せる部分が少ないものです。感情を全部セリフで説明してくれたりもする。
お客様扱いの答えがある説明、わかりやすい感情表現に慣れてしまうと、自分で考え感じねばならないことを不親切と思うようになったり不快に感じたりするようになります。
そういうものが売れがちな世の中でこういう映画がつくられ、きちんと評価されるアメリカは様々な点でガタがきているけど、まだまだ大丈夫だなと思いました(そして日本はあまり大丈夫じゃないと思った)
「自分の部屋がキャンピングカーみたいなもんだよね」
「うん、一番安心する」
「このちっちゃい自分の領域に守られて漂ってる」
「モリッシーの歌詞を刺青にしてるじゃん。もうそこから信用するね」
「アマゾンで全然働けるよ。掃除とか、まずいコーヒー作って配ったり」
「できるできる」
2021.4.26
アカデミー監督賞、作品賞、主演女優賞おめでとうございます。
中国人、女性、30代
日本では受け入れられない要素がある(嘆かわしいことに)かもしれないし
監督が漫画好きということが話題になるけど、そういう本筋とは違う自分たちにわかるラベルを貼って物事を引き出しに入れようとするの、やめたほうがいいと思います。
とりあえず見て。話はそれから。