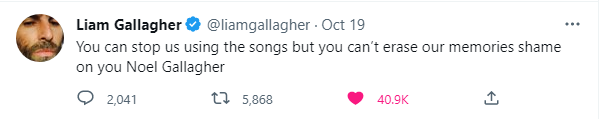2022/11/26
最近の眉毛兄弟 ネブワース22
リアム・ギャラガー ネブワース22 見てきました。
オアシスから26年ぶりのネブワース公演のドキュメント映画
いやいや、人って50近くなって成長するものですね!
ウォッチャーのざっくり感想
・病気のちっちゃい女の子が喜んでくれてよかった!なによりも!
ちょっと天才児なんだろうな…大変な病気で生きるの大変だからこそ、リアムの野生じみた乱暴なピュアに惹かれたのでしょう。
前に幼稚園に行ったときも小さな女の子に「かわいいわね」っていわれてたし。
いきものとして同じレイヤーなんだろうと思います。
・ジーンがそんなとこにいた!!!
ドラム叩いてました!
多分デビ―が「音の出ないヤツならいい、でもスタッフではないからちょっと映すだけ」と許可したんだろうと推察。
・ママ、ペギーを招待
親孝行したね!!
ノエルなんか50歳のパーティーにもよばなかったのに。
ヘリコプターで会場まで連れてって、さらにデビ―が手を添えてつきそってくれてました。
友達「なんか髪を染めた女の子、あれ看護婦じゃないかと思って。デビ―ならそこまで手配する」
それは気づかなかった!さすがです。
・デビ―が相変わらずで安心
後ろからついて歩く姿、完全な犬使い。
マネージャー、「リアムは周囲に優れた人間がいれば、とてつもないことができる」
一人ではどうしたらいいかわかりませんが
そう、優秀な人に囲まれてこその今。
本人もそれをわかってて、昔はチャラチャラしてバカだったと反省。えらい。
・本当はバンドがやりたい
ソロのネブワースという成功を得ても思うのはオアシス。
ノエルはオアシスの歌を使わせないとか、オアシスファンが歌うことを批判するとか、オアシス一番思ってるのはリアムなのに気の毒です。
ノエルの新曲や言動のダサさ、ほんと、弟の声あってのオアシスだって認めてください。…しょっぱすぎ
・エンドロールに DJ ポール・ギャラガー
さすがに今回はカメラマンとしては出てこなかった、映りもしなかったニートの長男ポール
多分デビ―に厳しくされているんだと思うけど、エンドロールに出てきました。DJって
・レノン、彼女と見に来る
ところが映ってました。モリ―は来たのかな…
ギャラガー一族の定点観測ができてよかったです。
ボンへは闘病中だけど、きっと見てたね。早く帰ってきてほしいですね。
「イギリスの階級意識の強さにちょっとびっくりした」
「労働者階級、庶民階級って、40代だけじゃなくて10代や20代もいってる」
「労働者階級じゃないのってなに? 貴族? 貴族そんなにいるの?」
「日本は士農工商ぜんぶ労働者だから感覚がわかんねえな…公家や将軍家に対しておれたち労働者階級って思わないじゃん」
「リアムは魂がブルーカラーだからね、セレブ気取りのノエルとは違う。そこが愛され」
「白いパーカーだったね。26年前も着てたけど勝負色なのかな」
「自分がかわいく見える色がわかってんじゃないの」
「あーそういう。まあ自分のビジュアルがいいと思ってるワンコだから…」
「毛並みぼさぼさだけどね」
「元気でがんばっててえらかったよ。ココナッツからこんなになるとはねえ」
「お酒飲まないで喉だいじにしてたしね」
「バンドメンバーもちゃんとしてたね」
「いい仕事にはいいスタッフが必要なんだよね」
「ハサミではない」
「弟に版権で意地悪するくらいしかできないあいつ…遠くなるばかりだね」