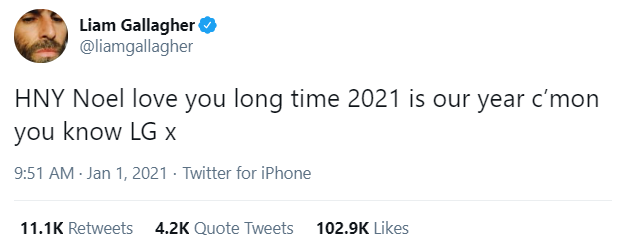2020/08/17
いや~暑いです。はじまりが冷夏だったので、今年は暑さが長引きそうな予感。10月くらいでも暑いんだろうなという気がします。
(過去のメモを見返したら、10月でも30℃とか11月でも半袖と書いてたので、この数年はそんな感じなんですね。温暖化。5月から30℃なので一年の半分は夏ということに…)
さて、夏季休業中、進撃の巨人を一気読みしました。
一応、連載初期から読んでたんですけど、10巻あたりで一度ブランクがあって、それから22巻団長さよならでまたいいかな、となったのです。
巨人は人間兵器でした、外国がありました、なんだそうか~で止まっちゃったので。
どうもすみません! 浅はかで。ジャンピング土下座。
最新刊までがっちり面白かったです。破綻がない。
逆側の立場から描くのは、あぁ…みんな事情がありますよね、知ってますけど、という陳腐あるいは「じゃあどうすればいいんだよ!」と作者が制御しきれなくてややこしくなりがちですが、凄くうまくバランスが取れてて名監督の映画みたいです。
うちは兄弟をさらにどす黒くしたようなイェーガー兄弟。
わりと兄弟萌え性癖なんですが、全然萌えを感じなくて、ジークの絶対的な不快感が安易に萌えさせない強い意志を感じて、それがいい。
ほら、こう、萌えって眼を曇らせるから…。
幼馴染がグレちゃって、家のしがらみがやたら重くて、というのもNARUTO第二章っぽいです。
しかもサスケが主人公のNARUTO。こりゃ色々な意味でしんどい。
もうずっと目回りが黒い。アバを見てるジョルノくらい黒い。
まだ父権とエンタメのインチキ自己流社会学みたいなのを引きずってるので、世界とイェーガー兄弟と父親について考えていました。
父権というのは現実の家庭ではとっくに崩壊しているのに、そのイデオロギーは社会に連綿と亡霊のようにとりついている。
イニシエーション=成長のための通過儀礼とすると、エレンが父親を食べて巨人の力を引き継いだというのは一方的で記憶に残っていなかったため、その役割を果たしていません。
イニシエーションではない父親殺しにより受け継がざるを得なかったものによる世界破壊は、まさに終われない昭和ゾンビに対する平成の息子といえるのではないでしょうか。
『お前が始めた物語だ』
だからお前が終わらせなければならなかったのに。
俺は父親の被害者→こんな世界に生まれてこなければよかった→子どもなんか生まれなければいいよ民族安楽死、はジークという後昭和期~平成前期の子供で、
生まれてきたから自由を求めて進み続ける
なので俺の大事な人たち以外を全部殺す(…!)
は平成中期以降の子供という感じがします。
島の中にいる自分と仲間を守るためなら、外は全部いらない。
いやもう危険! 早くあの子止めてやって! みんなの力とやらで!
平成前期のこじらせエンタメ代表であるエヴァンゲリオンでは、父親というのは権力者で理不尽で抑圧的なもの、という捉え方で、そこには逆説的な「超えるべき壁」としての父の絶対性が厳然とありました。
ジークはある意味碇シンジのベクトル上にいるともいえます。
そして、お兄ちゃんがお前を救ってやるからなエレン、というのは、そうすることで虚空にいる自分が父親に成り代わる手段なわけですが、結局自己中心的に空回りするだけで何ものにもなれないまま沈んでいくのです。
グリシャ・イェーガーもその父親の在り方により人生が変えられたことを思うと、グリシャからジークまでは終われない昭和の中から抜け出せない人といえます。
エレンは違います。エレンにとって父親は壁ではないです。もっといえば「破壊された壁」です。彼が壊したのではない。グリシャは既に崩壊しているのです。そういう意味で、あるように見えているけど終わっている昭和の亡霊なのです。と、思います。
いずれにしても、少年雑誌の大ヒット漫画の展開として画期的ではないかと思います。
あまり最近の漫画を読んでいないので、自分でも知ってるくらいのメジャー作品の範囲ですが、だからこそすごいというか。
少女漫画では、父権に対する懐疑というのはそれこそ70年代からありましたが(現在の少女漫画がどうなっているのかは知りませんが)少年漫画では長年、血族であれ象徴であれ敵であれ父親とは「超えがたく強く大きく頼もしい存在」であったわけです。頼りないお父さんや、ちゃらんぽらんのダメ父や、家族を顧みない父親というのも、結局わかりにくいけど大きな愛で家族を守っていた、という形で、少なくともメジャーな作品ではそのように描かれてきたと思います。(平成の代表的少年漫画であるワンピース、ハガレン、ハンター、キングダム、銀魂など)
お父さん(のような人)はすごい、僕もお父さんみたいになるんだ。現実にはもう崩壊しているのに、ドリームとして続いていく父権制があったのです。
少女向けの「父権社会での抑圧と生きづらさ、そこにずっぽり入った母親もしんどい、無理」は、世の中的には女子供の話で、つまりいずれ父となる能天気な少年たちには関係なかったのでした。
でもそこから、いや、いまどうなってる? おかしくない? 終わってない? 終わってなきゃいけないのに終わってないよ? 乗っかってきた「男にとって正しい」ものに従っていればよかったはずなのに、実際は誰も守ってくれないし、導いてくれないし、頼りになんかならなくて、昭和の父からもらえるはずだった既得権は取り上げられ、先細りの未来を押し付けられ、あげく自己責任とか言われる。
それって騙されてたんじゃない?
というところに王道の少年向けエンタメが来たというのは、遅いよ!という感触もありますが、いまだに死にきれない昭和が好きで疑わない人もいるので、やっぱり画期的だなと思うわけです。
あと、少年向けでは父だと共感が遠すぎるのか兄とか先輩がその身近な代替的存在だったりしますが、進撃はお兄ちゃんどうでもよすぎて新鮮。
※少年少女向けというのは読者性別比率ではなく、掲載誌のコンセプトが少年少女向けということです。
では、「俺の自由を求めて不要な旧世界を痛みをもって破壊する=連綿たる父権社会との決別」であるならば、若者はどんな新しい価値観をもてばいいのか。
昭和ゾンビに取りつかれ、大人になれない30年のまま閉じた平成はどこに行けばいいのか、どこにいけるのか、どうやって年を重ねられるのか。生きていけるのか。
31巻では、エレンのやり方は間違っている、世界を救いに行こうみんなで、というところで終わっていましたが、では救われた世界が果たしてその後どうなるのかは本誌を見ていないので謎です。
どんな回答を提示するのか、そもそも回答なんてあるのか、「森の中から出られなくても出ようとし続ける」なのか、ちょっとわからないですが、思いもつかない新しい世界があることを期待しています。
進撃は、驚くほど性差がない、というか、女性を性的な目で見ていないのもすごいです。娼婦や愛人とか立場として性的に搾取される女性はいるけど、そうではない女の子の肉体が性的に見られることのない世界というか。説明が難しいですが、同級生の女の子のお風呂を覗くような行為が入ってこない感覚というか。
かなり意識的にやっていると思うけど、いうほど簡単なことじゃないです。女とは男とはこうあるもの、肉体的にこう見られるもの、というのはものすごく深くこの社会で刷り込まれている感覚だから。
肉体的な性差というのは存在するけど、人が性別以前に人としてあるという感覚が当たり前の世界観。これもかなり新しいというか、ちょっと今までなかったほどのフラットさで、でもそれはホント当たり前のことのはず。
むしろ、普通のエンタメが女性を、あるいは男性をどういう眼で見ているか、描いているか、社会がそれを当然としているのが異常じゃないかという気がします。
閑話休題
家父長というのは社会制度における役割であって、個人ではないです。
でもその制度を構築しているのは個人の思考あるいは思考停止です。
システムは終わるし変わるし新たな価値観を探さなけらばならない時がある。
エレンが駆逐してやりたいのは人ではなく巨人という圧倒的な力に象徴されていたシステムであって、彼が自由を求めて自らの外にあるものを全部壊そうとするのは、ハンジさんが再三揶揄うようにわかりやすく反抗的で視野狭窄な若者だからです。そうじゃないと大きな変革をしようなんて思わないからです。
ジークが29歳であることを思うと、ジークの歪みと折れ方はそのまま平成の30年に重なる気がして、共感はできないけど切ない。でもまだこの先も人々は生きていかねばならないし、令和がどうなるかはこれからなわけで、その前に昭和と平成をちゃんと相対化しないと進めない気がする。のでこういう、愚にもつかないことを延々考えてるのでした。
誰かに伝えるというより、自分Aから自分Bへの、どうですかね、という問いかけなんですが、Bからは全然返事が来ない。仲良くしたいのに俺の村わりと分裂気味です。
ただ社会システムの生きづらさ、不自由さといってもいいですが、と人間の本質的な生きづらさは別物で、前者は改善できるもの、後者はできないものなので、「私の生きづらさ」「あなたの生きづらさ」が何なのか、考えて仕分ける必要はあると思います。そこを混同すると無意味に絶望的または楽観的になって、さらにそこに酔ったあげく変な自己満足に着地するから。
様々なものが終わっているのに、死にきれなくてゾンビになって他者を貪り、食っているのは恐ろしいことで、進撃の巨人とはその恐ろしさをものすごくダイレクトに感覚的に見せてくれる作品で、そこで個がどう生きるか、組織・仲間・絆の中で人を人として対等に描く作品で、凄いなと思いました。唐突に読書感想文な感じで、まる。